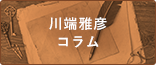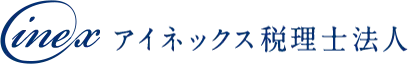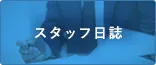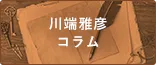高市政権誕生とどう向き合うか
高市政権誕生とどう向き合うか?
10月21日に高市早苗内閣が発足し、日本経済は新しい局面に入りました。市場ではいわゆる「高市トレード」と呼ばれる期待感から、日経平均株価は総裁選前の4万4,000円台から大きく上昇し、発足後には5万円台を突破、10月末には終値で5万2,000円台に乗せる場面も出ています。新政権の掲げる「責任ある積極財政」と大型の経済対策への期待が、投資家心理を押し上げている格好です。
もっとも、物価高や人手不足、地政学リスクといった構造的な課題は何ひとつ解決したわけではありません。この環境変化は、中小企業にとって「追い風」にも「逆風」にもなり得ます。
■日経平均上昇と「資産効果」
日経平均が史上最高値を更新していますが、単純に物価が上がるということは、価格決定権のある企業の売上が上がり、収益が増大するということですから、この傾向は続くものと思われます。
このことは、株式を保有する家計・企業に「資産が増えた」という心理的な安心感が生まれます。新NISAや企業型DCなどを通じて株式市場に参加している層も増えており、この資産効果は以前よりも広い範囲に及びつつあります。
その結果として期待できるのは、次のような動きです。
- 高額消費の回復(リフォーム、高級耐久消費財、旅行・レジャーなど)
- 成長分野向けBtoB投資の増加(IT投資、自動化設備、コンサル・研修など)
- 「将来不安」の軽減による、中長期の設備投資意欲の回復
BtoC企業であれば、「株高で懐が温かくなっているお客様」が自社のどの商品・サービスに反応しそうか、一度棚卸ししておく価値があります。たとえば、これまで価格転嫁に慎重だった高付加価値サービスでも、今なら値上げを受け入れてもらえる余地が広がっているかもしれません。
■類似業種比準価格の上昇と、中小企業の自社株評価
また、中小企業オーナーにとって特に重要なのが、「自社株評価」への影響です。事業承継やM&Aで使われる株価評価では、上場企業の類似業種の株価指標(PERやEV/EBITDA倍率など)を参考にするケースが少なくありません。
上場企業の株価が上昇し、同じ業種のマルチプル(倍率)が切り上がれば、同じ利益水準でも、自社株の評価額が上がる方向に働きます。これは、オーナーにとっては「見えざる資産の増加」を意味します。
プラス面としては、
- M&A売却や資本提携の際に、有利な条件を引き出しやすくなる
- 自社株式を担保とした資金調達余力が高まる可能性がある
といった効果が期待できます。
一方で、評価額の上昇は、
- 相続税・贈与税の課税価額の増加
- 後継者への株式移転コストの上昇
という形で跳ね返ってくる可能性もあります。
特に、今後5〜10年で本格的な事業承継を予定している企業にとっては、「高市政権下の株高」をどう位置づけるかによって、最適なスキームやスケジュールが変わってきます。株価水準・業績・金利(株価が高く、金利もやや上昇している局面)をセットで見ながら、承継対策を設計・アップデートしておくことが重要です。
■投資減税・補助金への期待と「選別」の時代
政策面では、高市政権は「物価高対策」と「成長投資」を両輪とする経済運営を掲げています。ガソリン税・軽油引取税の旧暫定税率廃止、電気・ガス料金の支援、中小企業・小規模事業者への資金繰り支援など、コスト高への即効的な対策が最優先に位置づけられています。
同時に、AI・半導体、GX・DX、防災、サイバーセキュリティなど17の戦略分野への集中的な支援が掲げられ、企業アンケートでは約4社に3社が高市政権の経済政策に一定の効果を期待していると回答しています。
今後、中小企業にとって鍵となりそうなのが「投資減税」と「選別型補助金」です。
- 設備投資額の一定割合を法人税から差し引く「投資税額控除」
- 投資初年度に減価償却費を一括計上できる「即時償却」
- これまで中小企業を中心に適用されてきた枠組みを、大企業まで広げる案も議論中
といった内容が成長戦略会議で検討されており、「給付から投資へ」「ばらまきから選別へ」という方針が明確になりつつあります。
ポイントは、「投資をする企業ほど、税制・補助金の恩恵を受けやすくなる」という方向に政策がシフトしていることです。
高市政権の発足は、日本経済にとって一つの大きな転機であると同時に、中小企業にとっては「選別される時代」の幕開けでもあります。
そのためには、株高による資産効果を享受できるビジネスモデルを強化し、投資減税や選別型補助金の対象となる投資機会をうかがうことが重要となります。
同時に、事業承継を考えている中小企業にとってはアゲンストとなる「類似業種比準価格の上昇」に伴う自社株の上昇が、将来の過度な負担となる前に、事業承継対策を再設計し、着実に実行することが、喫緊に取り組むべきこととなるでしょう。
そして、何より高市政権が、より長く続き、将来の見通しが明るくなることを大いに期待している今日この頃です。
令和7年11月14日
アイネックス税理士法人
代表 川端雅彦
2025/11/14