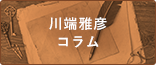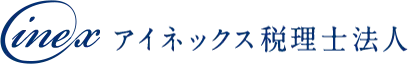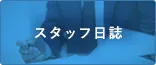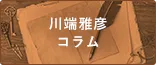前倒しされた最低賃金の引き上げ
厚生労働省の審議会は都道府県ごとに定める2025年度の最低賃金について、全国平均で時間あたり63円を引き上げ、全国加重平均で時給1,118円を目安とすることになりました。これは、24年度改定額の51円を上回り過去最大の上げ幅となります。
この方針は、前・岸田内閣が打ち出した「2030 年代半ばまで」に地域別最低賃金(全国加重平均)1500 円の目標達成時期を、石破内閣において「2020 年代中」に前倒したことによります。
このことは、多くの企業にとって人件費負担の増加を意味するだけでなく、例えば飲食業などのパート比率の高い企業においては、時給単価が引き上げられることにより、130万円の壁に到達する労働時間が短縮され、働く時間を抑制するという「労働力確保」の問題にも影響を及ぼしてしまうことになります。
それ以外にも、当然のことながら、中小企業や労働集約型産業では、直接的なコスト上昇が収益を圧迫し、経営戦略の見直しを迫られるケースが増えると考えられます。
しかし、この局面を単なる「コスト増」というマイナス視点だけで捉えるのではなく、「生産性向上やビジネスプロセス改革の契機」として捉えることが必要となります。
一人当たり生産性の低い企業に見られる傾向として、仕事があるから人が増えるのではなく、人が増えるから仕事が増えるという「パーキンソンの法則」が当てはまるケースがよくあります。
例えば、総務や経理部門において、2人で十分だろうと思われるのに、5人もの人を配置していることがあります。
こういった場合には、そもそもその仕事は必要なのか?価値があるのか?という質問を投げかけ、意味がないと判断されたなら、やめてしまうことによって業務が削減されます。
仮にその仕事に意味があるなら、自動化することによって置き換えることができないかを吟味すれば、多くの間接業務が合理化されることになると思われます。
営業マンにおいても、その活動をよく観察すると、業務日報や経費精算に多くの時間が割かれ、お客さまとの面談に使うべし時間が制約されているケースなども見受けられます。
一般的に営業においては、顧客訪問数と面談時間に比例して売上高が増加する傾向にあるので、こういった場合では、ITツールを活用したり、先ほどの間接部門の人員削減で生じた余剰人員を、営業マンのバックオフィスとして配置転換することにより、営業生産性を引き上げることも可能となります。
また、御用聞きセールスを売り上げの源泉の一つとして営業活動をしている企業なら、その業務自体をWEB経由に置き換えることにより、営業マンなしで売り上げを確保することも可能となります。
購買業務においても、生成AIを活用し、自動化すれば発注ロスも減り、余剰ストックを抱えるリスクも軽減されることとなります。
新しい分野への挑戦や、新商品の開発には、多くの投資や時間が必要であり、大きなリスクが伴い、中小企業にとっては大きなハードルとなります。
しかしながら、現在の売上と限界利益を、現在の人員の3分の2の人数で実現できるという生産性向上を達成できれば、少なくとも現状は維持できることになります。
そして、そのビジネスプロセスの変革において「生産性」という概念が全従業員に浸透し、生産性が低い企業の淘汰による残存者利益を吸収することも可能になると思います。
以前のコラムの繰り返しになりますが、最低賃金の引き上げは、変革の契機と捉えることが、変革の第一歩だと思うのです。
令和7年8月13日
アイネックス税理士法人
代表 川端雅彦
2025/08/13